平成19年9月の言葉
「ありがとう」言われるように
言うように
We should live so as to appreciate
and be appreciated.


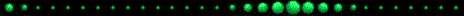
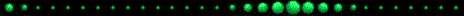
いろいろな「ありがとう」
舟橋左斗子さんが、「ありがとうを言わない国」で
ミャンマーを旅した時の話しを書いています。
日本人なら誰でも、ごく自然に「ありがとう」と口に出るのですが、
同行のガイドとドライバーから
ーありがとうはもうやめてくれーと言われたそうです。
その理由は
した方は・・・「ありがとう」と言われると、「いいこと」を相手にあげて、
相手から「ありがとう」をもらう。
だから、折角したよいことが帳消しになってしまう。
してもらった方は・・・「ありがとう」と言うことで、してもらったことによって
受ける「借り」を「ありがとう」と言う言葉で半減させようとする。
更に、
ミャンマーは「ありがとう」を必要としない許容力のある国だった。
人々は、持っている限りのものを人に与えることのできる
大きな拘りのない心をもっていた。
・・・イスラムの社会でも、与えた側が幸せであり、
与えた側が礼まで言う。
旅するうちに、「ありがとう」をベースに動いている
私達の社会(日本)の方が特異なのではないかと思えてきた。・・・
さて、皆さん、「ありがとう」の国際感覚をどう思いますか?
日本では、「ありがとう」は幸せになるための最も大切なキーワード。
例えば、
「ありがとうを伝えていくと、更なる幸運が」
「辛さをありがとうにしたら幸せがやってきます」
「ありがとうのパワーで、心がハッピーに」
「ありがとうは神様を呼ぶ声だった」
「ありがとうで対人運、仕事運、恋愛運がアップ」
「ありがとうで胃の痛みが消えた、便秘が治った、痛みが取れた、、、」
「ありがとうを言った分だけ、自分にありがとうが返ってくる」
こんな本もあります。
「人間、生きているだけで、ありがとう。
ありがとうを言うだけでいいことがいっぱい起きる」
「人生を変える言葉、ありがとう
絶対、運がよくなる感謝法」
「世界一簡単に幸せになれる、ありがとうの魔法」
「笑顔とありがとうの魔法」
正に、ーありがとう、ありがとう、ありがとう、、、、、ー
の国なのです。
海外を旅し、物売り、物乞いに金品を施した時、
相手から「Thank youありがとう」なんて言われた人は
ほとんどいないと思います。それどころか、
ーオレのお陰で、オマエはいいことが出来たろうー
そんな感じですね。
(「ありがとう」くらい言えないのか、
と腹を立てている日本人も多いと思いますが)
佛教では、無財の七施
<眼施(がんせ)、和顔施(わげんせ)、愛語施(あいごせ)
身施(しんせ)、心施(しんせ)牀座施(しょうざせ)、房舍施(ぼうしゃせ)>
を説きます。
相手に何も求めない、「ありがとう」の言葉さえも、
自分が今、出来ることを施す。
それが無財の七施なのです。
今、自分が出来るのは、してあげることが出来る相手がいるからです。
だから、相手から「ありがとう」の言葉をもらうのではなく、
相手に「ありがとう」の言葉を差し上げるのです。
これが佛教の基本的な立場だと思います。
日本では、何時から「ありがとう」が魔法の言葉になったのでしょうか?
松下幸之助の言葉に
「ありがとうと言う方は、何気なくても、言われる方は嬉しい、
ーありがとうーこれをもっと率直に言い合おう。」
こんな言葉が「ありがとう」ブームに火を付けたかもしれませんが、
この辺で、「ありがとう」を再考するのもいいかと思います。
何かをして頂いたから「ありがとう」なのではない。
合掌の心で、あなたのお陰で善行を積まさせて頂いたから、
「ありがとう」。
いや、「ありがとう」ではない、
「ありがとうございます」でした。
南無阿弥陀仏
釧路浄土寺 わたべ徳史

